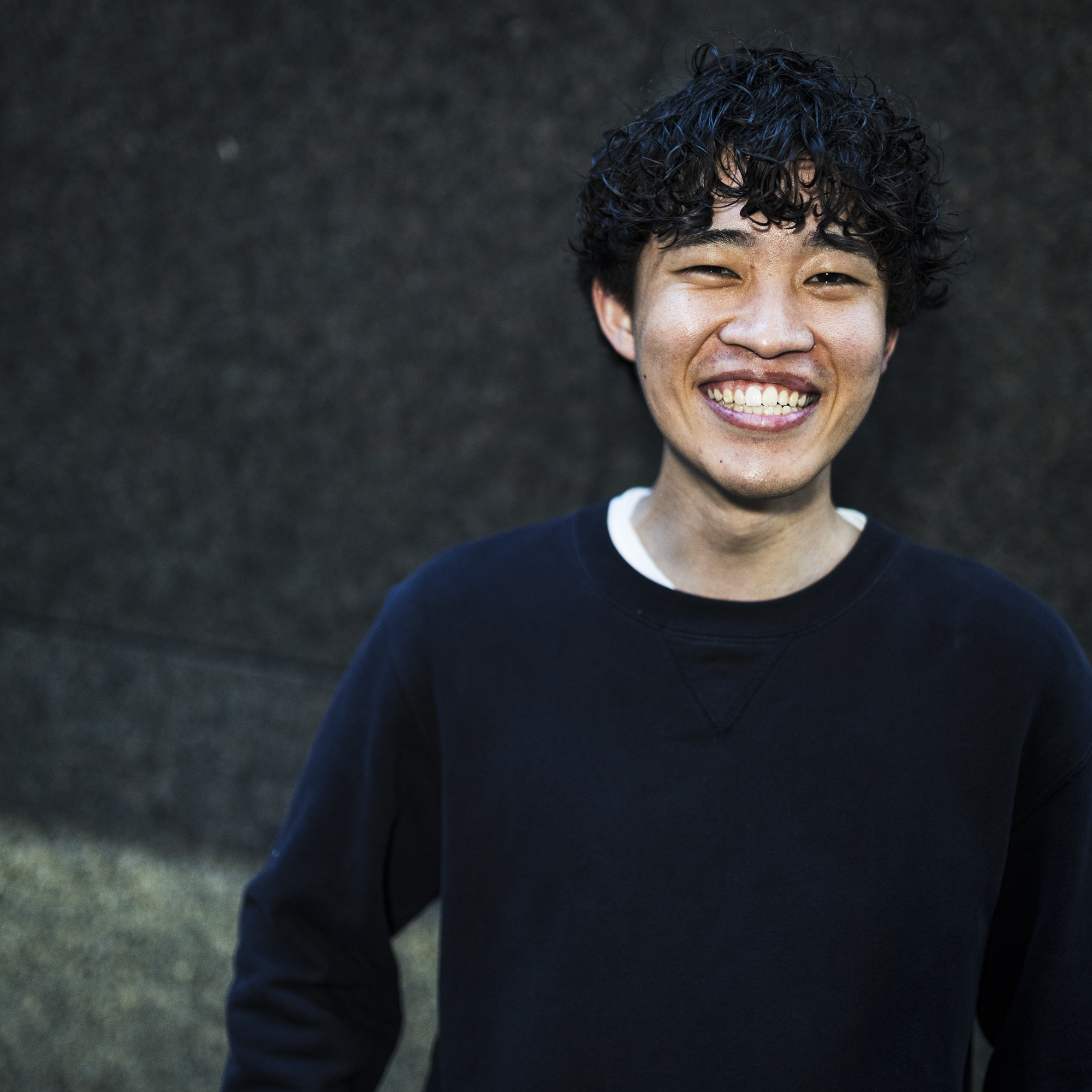いまのクルマ、本当に“持続可能”? 名車から考えるデザインの賞味期限 アルファGTV/クーペフィアット
公開 : 2024.07.23 06:25
・いまのクルマが失った個性
・90年代を彩った2台から考える
・永く愛されるデザインとは?
2台のクルマ、2人のデザイナー
クルマにかぎらず工業製品は、機能だけでなくそれを内包するデザイン抜きには語れない。そして機能もデザインを左右する。表裏一体の関係にある。
突き詰めれば、ヒトが乗り込める空間を4つの車輪で支え、走らせる動力源をまでもを格納するカタチがクルマであるわけだ。クルマをより速く走らせようとすれば流線型に、乗員により広い空間をもたらそうとすれば背が高くなる。

「形式は常に機能に従う」とは、20世紀初期の米国人建築家L・サリヴァンの言葉だ。建築とカーデザインとは必ずしも同一視できるとは限らないが、この言葉が世に出てからの100年あまり、設計者の行動をあまねく支配してきた一語であるといえよう。
ここに、2台のクルマがある。アルファロメオGTVとクーペフィアット。いずれも1990年代半ばに彼の地で生を受けた、イタリアンクーペだ。
この2台の線を引いたのはそれぞれ、イタリア人のエンリコ・フミアと、米国人のクリス・バングル。世に出てからおよそ30年を経た2024年のいまをもってして「何物にも似ていない」ショッキングな造形だ。一度見たら目に焼き付いて離れない。「忘却」「風化」といった類の形容は、およそこの2台には無縁であるといっていい。
遠戚にあたる2台が我々にもたらしたインパクトは、どうして色褪せないのか。実車から紐解こう。
哲学に基づく「意味のある」造形
GTVの線を引いたフミアは、1980年代の終盤、同じくアルファロメオで164を手がけた。
スクエアで端正なフォルムの3ボックスセダンには、盾をかたどった伝統のグリルがフロントに掲げられる。この164の側面に重ねられたプレスラインが、のちのGTVのインパクトを密かに予感させる。

GTV、およびそのオープンモデルであるスパイダーのスタイリングのハイライトは、大きく切り込みが入るフロントフェンダーとキャビンにほかならない。見る者の視線を釘付けにするこの鮮烈なプレスラインには、いうまでもなく機能の裏付けがある。それはボンネットの分割線であったり、ドアオープナーであったり。決して前衛的で目を惹くだけの造形ではない。
斜めのプレスラインに隠されたドアオープナーに指をかけてドアを開くと、外まわりに比べると常識的な造形のインテリアが広がる。ドライバーズシートに収まると、接近したフロントスクリーンやこちらを向いた計器類が、否が応にも積極的なドライビングを訴えかける。
シフトをローにいれ、徐々にクラッチペダルを離す。セカンド、サードへと、シフトアップ。2.0L V6ターボは低回転域こそトルク感に欠けるが、ガスペダルを踏み込むほどに、こと3000rpmを超え過給が始まると、はじけるような加速をもたらす。
そこからは前に前にとせき立てるGTVと、みずからの理性とを闘わせる作業だ。今となってはビッグパワーとはいえないパワートレイン。跳ね上がる回転計の針に呼応して高まるV6サウンドが、緊張を高める。
アルファGTVは、強いウェッジシェイプが効いたエクステリアから受ける印象そのままに、前のめりにドライバーを盛り立てる。カタチとナカミが実によく整合した1台といえよう。