【ときに厳しく、ときに優しく】自動運転トラックの要素技術検証開始
公開 : 2024.12.18 11:45
実用化に向けて、わたしたちができること
要素技術検証に使われるトラックは、荷室の左右に自動運転の実証実験中であることを示す文字が大きく掲げられているほか、フロント・サイド・リアに識別用のグリーンのマーカーランプが追加されているので、夜間でも識別できるだろう。
SAに入ってきたトラックは、ゆっくり駐車マスに向かうと、枠内にきちんと停車した。早速関係者が駆け寄り、停車位置などをチェックする。市場導入時には無人となるはずだ。そしてしばらくすると発進し、自動運転で本線へ向かう合流車線に入っていった。

過去に体験した乗用車の自動運転と比べると、動きはゆったりしているものの、停車位置は正確で、走行場所も違和感はないうえに、発進後にSAから出ようとする他車を発見すると先に通すなど、スムーズな動きだと実感した。
あとは本線上での制御がどうなるかであるが、他車の合流や工事箇所などの対策も入念にしているので、さほど心配はないだろう。すべてのトラックが自動運転になれば、追越車線に出てきて流れをふさぐような車両もいなくなるはずで、安全で快適な高速道路を目指すという点でも期待できる。
いずれにしても大事なのは、トライ&エラーの精神だろう。
自動運転は、人間で言えば赤ちゃんのような存在だ。もちろん安全性が第一だが、日本人にありがちな、絶対にミスは許さない、何事にも完璧を望むという考えだと、プロジェクトが先に進まず、国際競争に負けていく。逆に早めに実用化できれば、アジアやアフリカでの展開も可能となる。
だからこそ、ときに厳しく、ときに優しく育てていく気持ちを、高速道路を利用するユーザーにも持ってほしいと思っている。






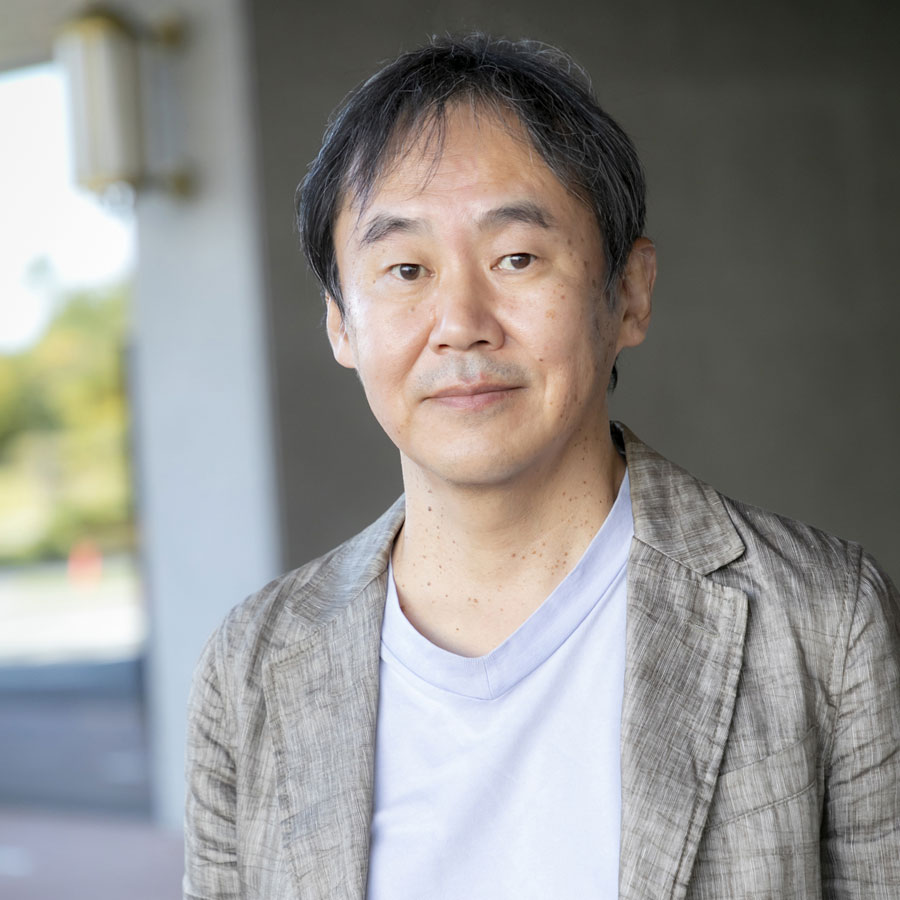

コメント