【詳細データテスト】ポルシェ911 適度なハイブリッド GT3に次ぐ走り 公道ではベストな911
公開 : 2025.03.29 20:25
市販911初のハイブリッドは、特殊なレイアウトのマイルドハイブリッド。重量増加は最低限で、出力とドライバビリティを高め、カレラGTSを独特な立ち位置にしました。公道で使うなら走りと実用性のバランスはベストです。
もくじ
ーはじめに
ー意匠と技術 ★★★★★★★★☆☆
ー内装 ★★★★★★★★☆☆
ー走り ★★★★★★★★★★
ー操舵/安定性 ★★★★★★★★★☆
ー購入と維持 ★★★★★★★★☆☆
ースペック
ー結論 ★★★★★★★★★☆
はじめに
ポルシェ911の世界で、劇的な変化というのはめったに起こらない。穏やかな進化が、常に基礎となってきた。また、設計工学的なレシピを大きく変えることを、ヴァイザッハの開発部門も、ツッフェンハウゼンの経営陣も避けてきた。
今の911は、水冷エンジンで、シングルかツインのターボが主流で、ボディサイズ拡大への対応策として後輪操舵を導入し、GT3には2ペダルも用意する。

新機軸は導入されても派手なものではなかったが、ここ10年以上にわたって課題とされてきたのが電動化だ。911も、ハイブリッド化が徐々に進行することは否定しがたい。そうなると危惧されるのが、911本来の元気な走りが損なわれることだ。ただでさえタイトなパッケージングに電気系を追加すれば、重量増加は避けられない。
911GT3Rハイブリッドが登場してから15年が流れた。ドライバーの隣には4万rpmに達するフライホイールジェネレーターが鎮座するこのレースカー、2010年のニュルブルクリンク24時間では、142周止まりで完走扱いにはならなかった。当時われわれはこのマシンを見ながら、911の市販ハイブリッドは、いかに欠点を減らした電動化を行うのか、思いを巡らせたものだ。
その後は、PHEVの918スパイダーや、超複雑な機構を用いたル・マンマシンの919ハイブリッドが登場し、そのノウハウを活かした911ハイブリッドの登場も近いのでは、と期待したのだが、なかなか実現しなかった。もっとも、フラット6を延命させるため中途半端に電動化して、ウェイトが1800kgになった、なんて911は、誰も望まないだろう。
しかし、ついに911の電動化が実現した。それは重量のかさむPHEVではない。今回のカレラGTSに搭載されるシステムは、ターボの頭文字を取ってT-ハイブリッドと呼ばれる。バッテリーは小型で、モーターは2基使用。エミッションを削減しつつ、ターボやGT系以外では望みえなかったパフォーマンスを獲得している。車両重量は1600kg少々だ。
はたしてこのハイブリッドは、シンプルなドライビングの楽しさや、911らしい日常での使いやすさを持ち合わせているのだろうか。























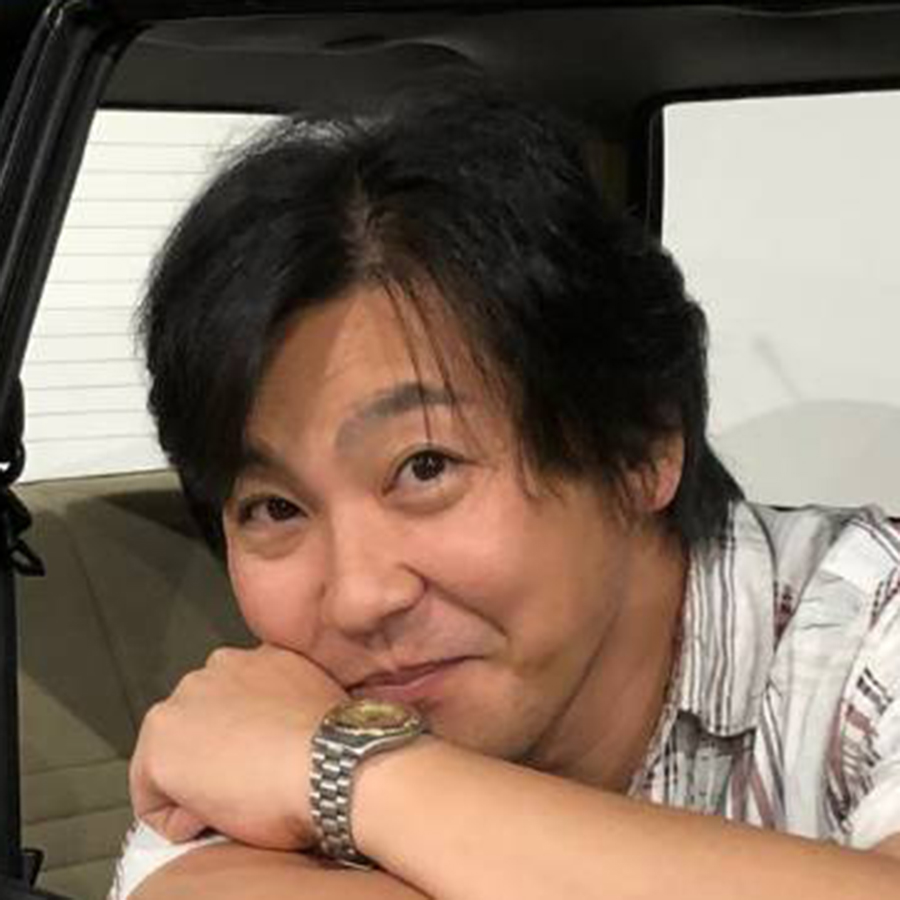

コメント